JR神田駅/新小岩駅最寄り

ゲシュタルト療法とは、「いま‐ここ」の気づきにフォーカスする体験的な心理療法です。現実で起きているこの場の
体験から、ありのままの自分に気づくこと、評価や解釈をせずその気づきをそのままを受け止めることを重んじます。
創設者のフレデリック・パールズは、あらゆる問題は過去にあるのではなく、「過去の未解決な問題が『いま‐ここ』の
現時点でも繰り返し表現されていることにある」と指摘しました。これは、大事なものは、どこか見えない場所にあるのではなく「いまーここ」に現れていることを意味します。
ファシリテーターは、セラピストという役割を果たすのではなく、ひとりの人間としてクライアントに関心を寄せながら関わり、一緒に過ごしている「いま-ここ」で起きている事柄から、クライアントが気づいていくプロセスをサポートします。現実に起こっている事柄に気づき、そのままを受け止めて、自覚的に選択していくことで私たちは、目の前の課題を乗り越えることができます。それは、結果的に悩みや葛藤が解消し生きやすくなっていくことに繋がります。
ゲシュタルト療法は、過去の出来事や心残りに引きずられず、未来に対する不安や恐怖を先取りせず、自分自身の感覚を信頼し、「いま‐ここ」の課題に自ら対応できるようになることをサポートします。

ゲシュタルト療法は、背景に哲学、心理学、生物学を取り入れています。ここで�は基盤となる概念について簡単に説明します。

「ゲシュタルト」とは、ドイツ語で「統合」「まとまっていく」「全体性」という意味を持つ言葉です。
「人間は現実世界や物事を、バラバラ(個別)に認識するのではなく、意味のあるひとつの全体像(ゲシュタルト)
として認識する」
「全体は個をすべて足した(総和)以上の意味を持つ」という、ゲシュタルト心理学の概念を取り入れています。
私たちはバラバラに知覚したものを、意味のある一つのまとまった全体像として、構成し、認識します。



これは「ルビンの壺」という図です。
白地に意識を向けると二人の横顔が、黒地に意識を向けると壺が認識できます。人の横顔を認識している時、黒地は背景となり同時に壺の形は認識されません。同様に壺を認識している時、白地の人の横顔は背景となり認識されません。これはゲシュタルト心理学の「気づきの原理」という概念です。人は一時にひとつしか認識することはできず、それが瞬間的に入れ替わり、複数を認識しているように思えるのです。意識に上っている対象は「図」と言われ「意味のあるもの」として認識されます。認識されていない背景となっている対象を「地」と言います。
私たちが気づいている対象(図)は、「意味のあるもの」として自分自身で(無自覚でも)選択してしているものです。

ゲシュタルト療法では人間を「他の動物よりも優れた特別な存在」としては捉えず、「生物」(有機体)として見ます。私たちには生物として、生命を維持するために、現実世界(環境)の変化に応じて、自身の状態を調整し持続的にバランスを保ち続ける機能〔恒常性・ホメオスタシス〕が備わっています。
暑さの日には汗をかいて体温を下げたり、暑さを凌ぐために移動したくなり行動を起こすことや、体内の水分量が不足している時は、喉の渇きが起こりそれを感じて実際に水分を補給したりすることがこれにあたります。ホメオスタシスという機能が作用することで自分の体(生体)に起こった事柄から気づきが起こり、今、必要なものを選択し取り入れて生命を維持することができます。私たちは、自分自身が快適な状態で生きていくために、自分自身で気づき、選択していくことができます。
上記は生理面の説明ですが、ホメオスタシスは感情を含む精神面でも同様の働きがあります。



創設者のフリッツパールズは、この気づきを三つの領域に区分けしました。
現実世界への気づき、からだの内側への気づき、思考の世界での気づきの領域です。
◆三つの領域
1.現実世界(外部領域)
2.からだ(皮膚)の内側の世界(内部領域)
3.思考の世界(中間領域)
1.現実世界(外部領域)
身体の外側の環境を指します。
私たちは五感(視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚)を通して現実世界を認識し(気づき)ます。
2.思考の世界(中間領域)
人間は脳の機能により思考、記憶、推測をしたり、価値観を取り込むことや知識を蓄え解釈することができます。
3.からだ(皮膚)の内側の世界(内部領域)
身体の内側を指します。
この領域には、痛み、眠気、空腹、症状、呼吸の状態や部位に生じる身体的な感覚、感情、気分など精神的な感覚も、内部領域に含まれます。
私たちは健やかな状態では、無意識にですがこの三つの領域を、
瞬間ごとに行き来しています。それぞれの領域に触れてありのままを
認識することをコンタクトと言います。しかしながら、何かに気をとらわれている時は、ひとつの領域に留まっている状態となり、残り二つの領域にコンタクトを取れていません。例えば、思考レベル(中間領域)の想像にとどまっている時、現実世界にコンタクトができていないため、いくら想像しても答えや実感は得られません。それらを埋めようとして、繰り返し思考や想像することで補おうと堂々巡りとなっていきます。
このように三つの領域を往来できていない状態の時に、問題が起こります。
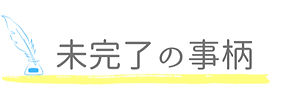
過去にやりたかったけれど何らかの事情でできなかったこと、成し遂げられなかったことや、それにまつわる感情、感覚、経験を「未完了の事柄」と言います。子供の頃、両親に反抗したかったけどできなかったり嫌だったけど嫌と言えず我慢し続けたこと、泣きたかったけれど人目があり思うように泣けなかったことなど、多かれ少なかれ誰の中にもあるものです。
欲求は充分に経験することで、満たされて沈静化していきます。喉の渇きを覚えて水分補給し、満たされると喉の渇きは消えて、別のことに気づいたり意識が向くように、欲求は充分に経験することで「図」から「地」へ反転していきます。意識に上がっているものを充分に経験し満たされることで、完了を迎えます。そして図と地の反転(入れ替わり)が起こり、新たな気づきが起こります。しかし、未完了の事柄は充分に経験されていないため、その欲求は体の中で残ったままになっています。そして、完了するまで、相似した状況の際に刺激され、何度もその欲求が繰り返し呼び起こされます。
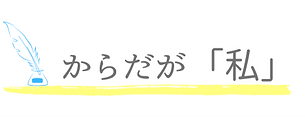
ゲシュタルト療法では、精神と身体を分裂させず、一つのものとして捉えます。私たちは悲しいときに、目が下がり口元に力が入って悲しい表情になります。怒りを感じた時は眉間に皺がより、目がつり上がるなど怒りの表情になります。いま、経験している体験や感情は、からだを通して表現され、身体感覚としても体内で感じられます。からだは私たちが自覚している以上にしぐさや雰囲気、動きや緊張を通して「今、ここ」で体験している感情や心を表現しています。他者との関わりにおいても言葉だけではなく、相手の表情や態度、しぐさなど全体から醸し出される雰囲気を察知します。
また、ボールを投げる動作や、匂いを嗅いだ時に突然、過去の記憶が思い出された経験はありませんか。私たちはこれまでの人生を、からだを通して外側の世界と関わって生きてきました。からだの動きや感覚、感情、記憶、理性など全ては繋がっています。今の姿勢や、しぐさ、動きに意識を向け、何を表現しているのかその意味(からだの声)に気づき、そのままを受け止めることで、分断されていた心と体が繋がり本当に自分が感じていたことや欲していたことに気づき統合されます。


ゲシュタルト療法では「私が見ている現実世界は、私の主観を通して認識しているため、実際の現実世界とズレがあるかもしれない」という現象学の立場をとります。これは、「自分の中に起こったことは自分の主観である」という事実を受け止めることを大切にしているためです。自分の中に起こった主観を絶対視せず、かっこに入れて横に置き、先入観や思い込みを通さずに、起こっている目の前の現象をそのまま見つめる立場をとります。それは、「ありのままに目を向けたときに、人は直感的に本質を捉えることができる」という概念が根底にあるからです。知識から得た情報や社会通念を照らし合わしその指標で相手を測るのではなく、目の前にいる人の存在やオリジナリティを重んじます。
それゆえ、ファシリテーターは、上下関係を作らず、優劣や正誤などの価値判断、評価も行いません。今日まで生きてきたひとりの人間として、対等にクライアントと向かい合い、今、ここで起こる現象を通して対話を進めます。

私たちひとりひとりが、実際に存在していることに焦点を当てた哲学が実存主義です。
人間は、「こう生きるべき」という本質を生まれながらに持っているのではなく、またどこか高尚な見えないところに存在の本質があるのでもありません。戦争や自然災害が起こる不条理な現実世界を生きて、いずれ死を迎える存在が私たちです。私たちはいつか迎える死の恐怖や無の不安、人生の孤独に悩まされます。その時に目を背けたり誤魔化したくなることもありますが、その不安や恐怖から逃げず正面から受け止めて充分に経験したときに、「それなら自分はどう生きたいか、どう生きるか」を選択することができるようになります。選択することで、選択した立場という責任を持つようになり、選択と責任によって、初めて「自由」がうまれます。どうするか選択して、自覚的に生きていくことで、その人ならではの独自性が創られていきます。

私たちは、素晴らしい能力や容姿を欲して、今よりも優秀な人間になりたい、変わりたいと望むことがあります。そのような状態では努力しても変容は起こらずにむしろ、変化から遠ざかっていくという考え方です。
それは、現在の自分自身を否定しているためです。そのままの自分を受け止めず、現実から目を背けていることになります。現在の自分を否定している状態から新しい自分自身には本当の意味で変容は起こりません。
立派な自己像を求めず、価値判断や意味づけに左右されず「今の自分」をそのまま、本当に受け止めたときに、変化は自然に起こります、これが「変容の逆説的理論」です。本当の変化は、ありのままの自分を受け止めて、自分自身でいることから始まります。

最後に、パールズが記した「ゲシュタルトの祈り」を紹介します。
私は私のことをする。あなたはあなたのことをする。
私はあなたの期待にそうために、この世に生きているのではない。
あなたも私の期待にそうために、この世に生きているのではない。
あなたはあなた、私は私である。
もし、たまたま私たちが出会うことがあれば、それは素晴らしい。
もし出会うことがなくても、それは仕方ないことだ。
参考文献
百武正嗣 「気づきのセラピー はじめてのゲシュタルト療法」春秋社 2009年
百武正嗣 「家族連鎖のセラピー ゲシュタルト療法の視点から」春秋社 2012年
倉戸ヨシヤ 「ゲシュタルト療法 その理論と心理臨床例」駿河台出版社 2011年
日本ゲシュタルト療法学会「JAGTゲシュタルト療法<トレーニング・テキスト>」2014年
日本ゲシュタルト療法学会「JAGTゲシュタルト療法テキスト<新版>」2018年
フレデリック・パールズ「記憶のゴミ箱 パールズによるパールズのゲシュタルトセラピー」 新曜社 2009年
